 美容・健康
美容・健康 インスタントコーヒーが体に悪いとされる原因はアクリルアミド!飲むなら有機JAS認証のインスタントコーヒーが安全でおすすめ
インスタントコーヒーの方が体に悪いとは限らない!どんなコーヒーが危ないかを正しく知って安全なコーヒーを楽しもう♪最後まで美味しく飲むための保存方法も紹介します!
 美容・健康
美容・健康 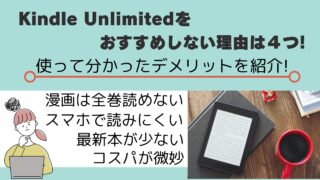 豆知識
豆知識 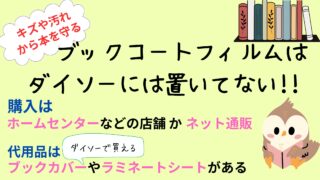 生活雑貨
生活雑貨 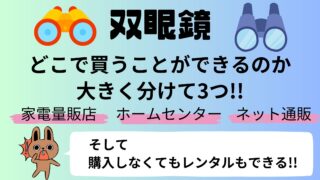 豆知識
豆知識 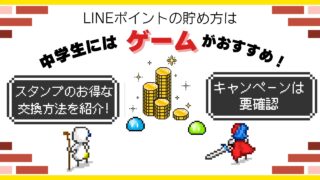 豆知識
豆知識 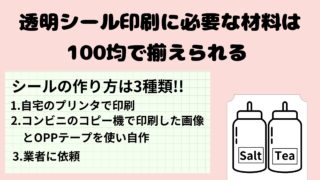 生活雑貨
生活雑貨 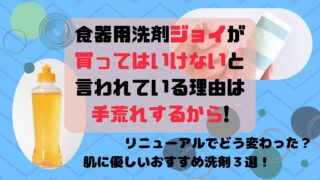 生活雑貨
生活雑貨 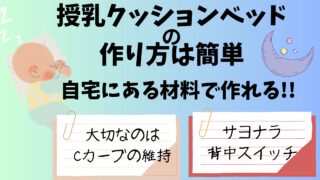 生活雑貨
生活雑貨 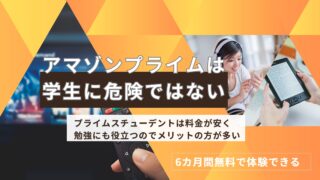 豆知識
豆知識 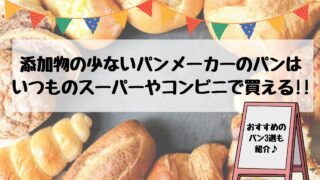 食品
食品